こんにちは、もちきなこです。
今回は、「言葉の認識のズレに気づく」と題しまして、学生時代から今までの経験で感じた、言葉についての認識のズレの部分の話をしていきます。普段の会話で、毎回意識しているわけではないですが、意識して話を聞いていないと論点がズレていたり、話がすれ違ってしまっていることがあるので、私の過去のエピソードも交えながら、「同じ言葉でも、人によってこんなに言葉の認識って違うものなのか」と気づく一端になれば幸いです。
言葉の認識ってなぜズレるの?
そもそも言葉の認識ってなぜズレると思いますか?答えとしては、「人それぞれの持っている前提によって、見方が変わるから」といえると思います。
例えば、下記の一文を読んでどんなことを想像しますか?
火が消えた
上記一文のみだと、ただ単に、何かの火が消えた状況を表しているだけだと思います。
では、下記のような前提があったら、上記一文「火が消えた」の解釈(言葉の認識)はどのように変わるでしょうか?
- 百物語などの怖い話をしている時
- 外でサバイバルをしている時
- キッチンで料理を作っている時
- 家に火がついていて、消火活動が行われていた時
1番は、「百物語で一つのお話が終わった際に、ろうそくの火を一つずつ消していく」という前提がある方であれば、「一つの物語が終わり、ろうそくの火が消えた」と解釈することができます。
2番は、「外でサバイバルをしていて、何もない状態から大変な思いをしてつけた」という前提があれば、「安全な場所を作ったり、料理したりするための、命綱の火が消えた」と解釈することができます。
3番は、「安全な場所にいて、いつでも火をつけられる」という前提があれば、「日常生活でよくあるキッチンコンロの火が消えた」と解釈することができます。
4番は、「火の大きさが大きく、家や人命に影響がある」という前提があれば、「家中に燃え広がっていた火がやっと消えた」と解釈することができます。
上記はそれぞれ、同じ「火が消えた」という一文に関する印象ですが、全く印象が違うと思います。
このように、私たちの毎日のやり取りでは、その現象の重要度や緊急性等の様々な要素が言葉の認識のズレによって、伝わり方に差が生じている可能性があります。特に、日々の仕事などで、同世代だけでなく、世代が違う方と接するときや、国籍が違う方と接するときに、この言葉のズレというものは大きくなる傾向にあります。
日本語の難しさ
私たちが日常的に使う日本語は、「行間を読む」言語という表現がある通り、全てを明示的に話していなくても、会話の流れや話しながら見ているもの、その時の状況などによって、話している言葉の意味を推測して会話を行うという、外国の方からしても高度なコミュニケーションを行っています。
例えば、簡単な省略の例でいうと、小学生で習う算数の問題で以下のようなものがあると思います。
AはBの何倍ですか?
上記の文章は、説明を増やしてよりわかりやすく書き直すと、下記のようになります。
AはB(をもとにしたとき)の何倍ですか?
括弧内の文章は、書かれていなくても、当たり前のことだと思い込んで、算数の問題を解いていた方もいるでしょう。けれど、私は学生時代に塾講師のアルバイトをして小学生を教えていましたが、このような行間がわからずに問題が解けないといった生徒もいました。
また、求めている内容がほとんど同じであるのに、言い回しが違うために、求め方がわからないといった問題もあります。上記の倍数の例でいうと、下記のような問題です。
AはBの何%ですか?
何%というのは、割合を表し、表記の仕方は違いますが、倍数の概念と考え方は同じです。そのため上記一文も、下記のように説明を増やすことができます。
AはB(をもとにしたとき)の何%ですか?
もちろん、外国語であっても、同じ意味の言葉は複数あることはありますが、日本語特有の婉曲的な言い回しでは、直接的に明示はしていないものであっても、言外に伝えていることが多いです。
特に、日本の文化的な背景として、「直接的に物事を表現するよりも、間接的に物事を表現する方が趣があってよい」といった考えが根底にあり、日本人同士の会話では、和を尊重し、察して動くという側面も見られます。
そして、文章内の助詞のひらがな(てにをは等)が一文字変わっただけで、全体の文章の意味が変わってしまったりすることもあります。それぐらい日本語は、文面の印象だけでなく、非言語のコミュニケーションが大きく影響する言語であり、少しの変化で認識のズレが起きやすい言語だということです。
ただ、昨今では、それぞれの個性などの多様性が尊重され、今までの日本の文化としての、暗黙の了解が通用しないことが 多くなってきています。もちろん全体のルールとしての法律等、守るべきものは変わっていないのですが、ビジネスマナーなどの基本的な社会人の在り方などに関しては、外国籍の方も増え、いろいろと許容される範囲も広がり、大多数が正解というような答えが曖昧になってきています。当たり前ではありますが、各共同体の中で、許されるもの、許されないものは違い、そのルールに則って日々を過ごしているため、特に違う共同体の方(違うルールに則って過ごす方)と関わるときにこの認識のズレが発生しやすくなります。
認識のズレを少なくするために
では、それぞれの認識のズレを少なくするために、私たちは、どのようなことを意識していけばよいのでしょうか?私の個人的な考えにはなりますが、第一前提として、「認識は必ずズレているものだ」として人との認識のすり合わせを行うということです。たとえ、同じ共同体に所属していて、家族であっても、長年の友人であっても、同じ会社にいて同じルールに従っていたとしても、着目しているところは違い、見えている世界も違い、育ってきた環境も違い、考え方も何もかもが違います。そのため、人と話すというのは、まず相手は他人であり、私とは違う考えを持った人であるという大前提のもと行われなければいけないと思います。認識がズレているからこそ、質問や確認をし、認識をすり合わせる必要があるのです。
認識のズレが発生する主な原因としては「知識量の差」にほかなりません。これは、具体的に言うと、世代間でのそれぞれの生きた環境の差(世代間ギャップ)や、そもそもの言葉としての理解力(語彙力の差)、今現在取得している情報の幅の差(多面的な見方ができるのか等)の様々な要素が絡んでいます。このような主原因を理解したうえで、実際の会話の内容に焦点を絞って質問や確認をしていくことで、認識のズレが少なくなると思います。
基本的にコミュニケーション力が高いといわれる人は、場の空気を読むのがうまかったり、相手に確認や質問をする頻度が多かったりします。その確認や質問の答えによって、相手の置かれている状況や感情を理解し、共感したり、意見を申したりができるからこそ、話が弾んでいくのです。
また、学校でも、会社でも、それぞれの共同体の中で、守るべきルールは規定されていますが、そのルールの範囲外でも、「あなたはなぜこのようにしないのか?あなたはなぜこれができないのか」という相手が主語になり、相手が何かをしてくれないという風な考え方をするのではなく、「私は何ができるのか?私は何をしてほしいのか?」といったような、自分を主語にする考え方を持つことで、日々のストレスも限りなく減らすことができるのではないかと思います。
基本的に相手の行動は変えられませんし、何も言わなくてもわかってもらえることはほとんどないです。そのため、人と話すときに自分の意見を言って、相手の意見も聞いて、お互いの立場を理解したうえで、相手を尊重しながらやり取りを行うことが大事だと思います。もちろん、合わない人と無理に合わせる必要はないですが、仕事上関わらないといけなかったりする相手の場合には、変えられないことに注目するのではなく、自分で変えられる部分に目を向けて改善していくしかありません。認識をすり合わせ、状況を詳細に分析し、問題点を小さく小さく分けていくことで、問題解決の糸口が見えてきたりもします。
私は前職が外資系の会社だったため、日常的に認識のズレをなくすということを意識していました。普段の会話ではここまで意識しなくてもよいのですが、仕事でのやり取り上、認識のズレが起きた場合に、仕事の進捗が遅くなるため、できるだけ相手と認識を合わせられように工夫をしておりました。もちろん、どんなにすり合わせていても、前提が間違っているということはたびたび発生するのですが、意識して話をすることによって、限りなくズレは減らすことができるようになります。
読者の皆さんも、この前提部分を意識して、人とのやり取りを行ってみて下さい。今まで意識していなかった、すれ違っていた部分に気づくことがあるかもしれません。
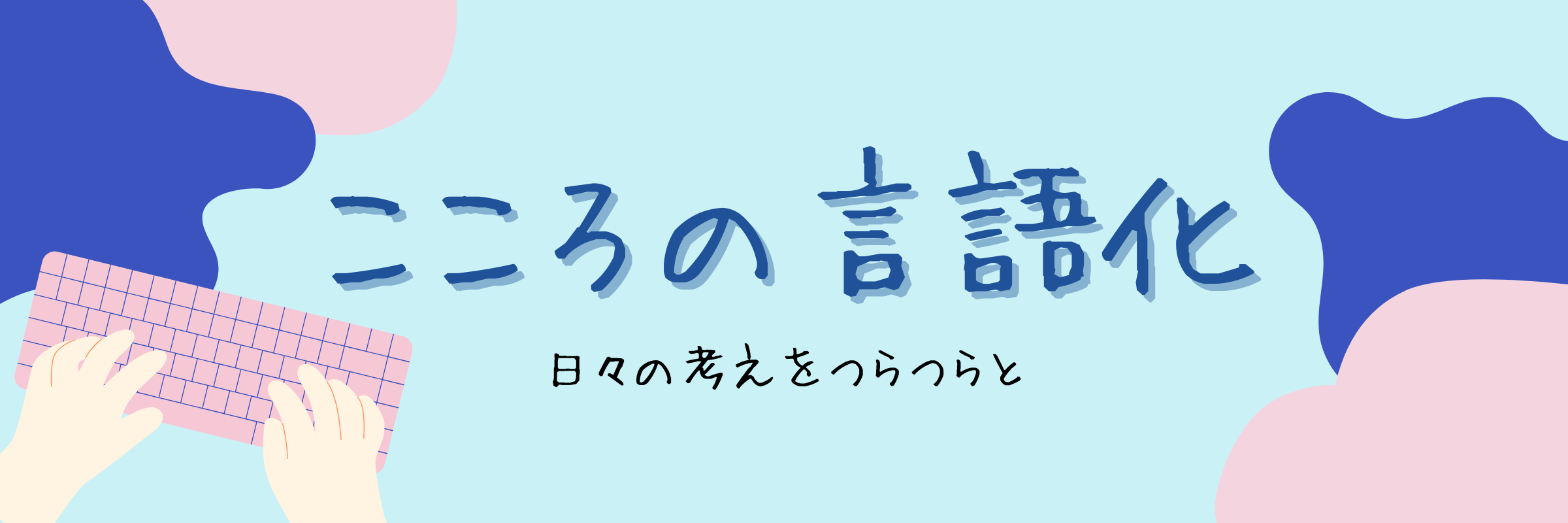

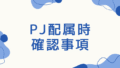

コメント